糖尿病を勉強しようと考えている方
- 血糖降下薬に強くなりたい
- 患者指導ができるようになりたい
- おすすめの参考書が知りたい
そういった方へ「糖尿病看護おすすめの参考書」について紹介します
記事の内容
1.参考書の選び方
2.解剖生理・病態生理のおすすめの参考書は
- 「病気がみえる 糖尿病・代謝・内分泌」
3.看護のおすすめの参考書は
- 「糖尿病ケア」
- その中でもおすすめの2冊を紹介
記事の信頼性
内分泌代謝内科で勤務経験があり、看護師歴20年の現役看護師です
これまで内分泌代謝内科・循環器・脳外科・消化器等で働いてきました
読者の方へのメッセージ
糖尿病は看護師として必須の知識です
最初は大変ですが一つずつ覚えて実践に活かしていけば大丈夫です
努力して得た知識と経験は「看護師として一生ものの財産」になります
この記事の目標
「糖尿病看護に自信が持てる」です
それでは詳しく見ていきましょう
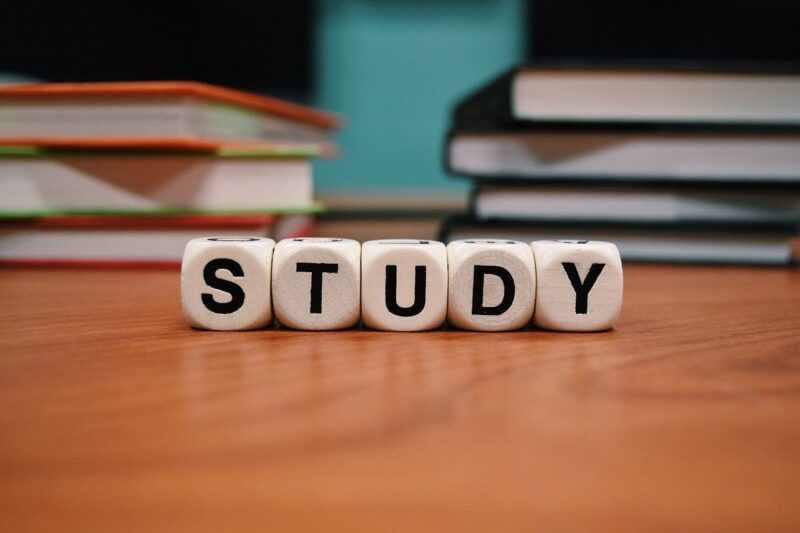
糖尿病内科 参考書の選び方
糖尿病内科の参考書は2つに分けて選びましょう
- 解剖生理・病態生理
- 看護
本来は1冊ですべてを学べる参考書があればよいのですが、どれかが足りないのが現状です
そのため「解剖生理・病態生理」と「看護」に分けて学習するのが効率的です
まず最初に「解剖生理・病態生理」を学習するメリットとおすすめの参考書を紹介します
「糖尿病 解剖生理・病態生理」おすすめの参考書
解剖生理と病態生理を学習するメリット
1.血糖を上げ下げする体の仕組みがわかるので
- いろんな種類の糖尿病薬が本当に理解できる
- 低血糖や高血糖時の対応が自信をもってできる
2.根拠がわかるので
- 自信をもって患者指導ができる
- 先輩や医師へ適切な報告ができる
糖尿病薬を覚えるコツは(各種内服薬・インスリン・GLP-1)の機序を理解することです
そのためには糖代謝・インスリン抵抗性・インスリン分泌・インクレチンといった知識が必要です
もちろん患者指導にも解剖生理と病態生理の知識は必須です
最初は大変ですが、一度しっかり理解できると、自信をもって看護できるようになります
病気がみえる 糖尿病・代謝・内分泌 メディックメディア
解剖生理と病態生理の学習におすすめの参考書は「病気がみえる 糖尿病・代謝・内分泌」です
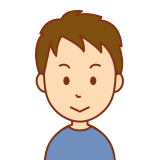
私も「病気がみえる 糖尿病・代謝・内分泌」を使っていましたが、専門病棟の内分泌代謝内科でも十分に通用する内容でした
| 最新の情報 | ◎ |
| イメージのしやすさ | ◎ |
| 解剖生理の詳しさ | ◎ |
| 実践向き | 〇 |
| 看護の詳しさ | × |
メリット
- 糖尿病専門病棟でも対応できる内容
- 写真やイラストが豊富でイメージしやすい
- 「症状→検査→診断→治療」の流れが理解しやすい
デメリット
- 看護が薄いため糖尿病看護専門雑誌(糖尿病ケア)を併用する
他の参考書との比較
- 解剖生理と病態生理の学びに最適
- 定期的に改定しており最新の知識を学べる
- 医師が使う略語や英語に対応しており実践的
病気がみえるシリーズの弱点は看護が弱いことです
次に「糖尿病看護」の参考書について紹介します
糖尿病看護 おすすめの参考書
糖尿病看護専門雑誌「糖尿病ケア」がおすすめです
私も「糖尿病薬の学習」や「糖尿病教育入院の患者指導」に活用していました
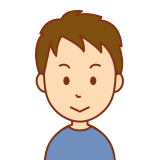
「糖尿病ケア」の良さは、学習しやすいだけでなく、臨床看護に活かせるところです
糖尿病ケア メディカ出版
| 最新の情報 | ◎ |
| イメージのしやすさ | ◎ |
| 解剖生理の詳しさ | 〇 |
| 実践向き | ◎ |
| 看護の詳しさ | ◎ |
今回は「糖尿病ケア」の中でも、最近でとくにおすすめの2冊を紹介します
- 1冊目は基礎から学びたい方
- 2冊目は専門的に学びたい方
それでは詳しく見ていきましょう
「糖尿病看護きほんノート」 糖尿病ケア 2020年春季増刊号 メディカ出版
- 糖尿病を基礎から学びたい方
- 最新の糖尿病薬や患者指導を学びたい方
この本の特徴
- 基本的な糖尿病の病態、治療を基礎から学べる
- 血糖降下薬・インスリン・GLP-1など最新の薬物治療を学べる
- 患者指導の基本も学べる
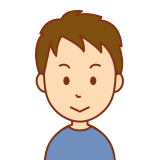
基本からわかりやすく解説しているので、糖尿病を基礎から学びたい人におすすめです
1章 糖尿病のきほん
- 病態生理、検査、診断
- 高齢者糖尿病、糖尿病合併妊娠、妊娠糖尿病
2章 糖尿病治療とケアのきほん
- 糖尿病治療のきほん、食事療法、運動療法
- 薬物療法のきほん(血糖降下薬、インクレチン関連薬、インスリン療法)
- 血糖モニターとインスリンポンプのきほん
- 血糖パターンマネジメントのきほん
第3章 糖尿病の合併症と併存合併症のきほん
- 糖尿病神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症のきほん
- 糖尿病足病変、フットケアのきほん
- 低血糖とシックデイのきほん
- サルコペニア・フレイル・ロコモティブシンドロームのきほん
- その他内容多数
第4章 糖尿病の患者指導のきほん
- 患者とのかかわりかた・接しかたのきほん
- セルフケア・生活全般の指導のきほん
- 個人指導・集団指導のきほん
- その他内容多数
第5章 糖尿病患者の心理・社会のきほん
- 多職種や患者家族とのかかわりのきほん
- 糖尿病患者の介護・地域包括ケアのきほん
- その他内容多数
「糖尿病のくすり 徹底ナビゲートBOOK」 糖尿病ケア 2021年秋季増刊号 メディカ出版
糖尿病を専門に扱う部署の方
この本の特徴
- 基礎から応用まで最新の糖尿病薬の知識を学べる
- 症例が豊富で、糖尿病内科の方には必携の一冊
- 食事摂取量が少ない時や内服を忘れた時などに、血糖降下薬を内服させる基準がわかりやすく解説してあるので、本当に看護に活かせる内容となっている
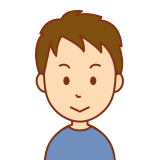
他科の方でもリーダーを取るような方であれば、医師とのやり取りに活かせるのでおすすめです
第1章 糖尿病治療薬の使いかたと処方のポイント
1.ビグアナイド薬、チアゾリジン薬の使いかた・処方のポイント
2.α-グルコシダーゼ阻害薬の使いかた・処方のポイント
3.DPP-4、SGLT2阻害薬の使いかた・処方のポイント
4.GLP-1受容体作動薬の使いかた・処方のポイント
5.スルホニル尿素薬の使いかた・処方のポイント
6.速効型インスリン分泌促進薬の使いかた・処方のポイント
7.経口薬の配合薬の処方のポイント
●第2章 インスリン製剤
1.インスリン療法の基本
2.超速効型インスリン製剤の使いかた・処方のポイント
3.速効型・中間型・混合型インスリン製剤の使いかた・処方のポイント
4.配合溶解・持効型溶解インスリン製剤の使いかた・処方のポイント
5.注射薬の配合薬の処方のポイント、糖尿病治療用注入デバイスについて
●第3章 血糖測定機器とインスリンポンプ療法
1 SMBG
2 CGM
3 iCGM
4 CSII
5 SAP
●第4章 糖尿病合併症・関連疾患の治療薬
1 糖尿病性神経障害
2 糖尿病網膜症
3 糖尿病性腎症
4 脂質異常症・ 高血圧症
●第5章 糖尿病患者が注意したいOTC医薬品・健康食品
1 糖尿病患者がOTC医薬品・健康食品を使用する際の注意点
2 知っておきたいOTC医薬品、 知っておきたい健康食品

おすすめの学習方法
勉強を続けるコツ
勉強を続けるコツは一度にたくさんの勉強をしないことです
もう少しやりたいなというところで終えるのがコツです
なぜなら継続が最も大切なことだからです
看護師人生は受験と違って1年や2年で終わるのではなく何十年も続きます
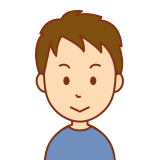
毎日コツコツ少しだけがポイントです
具体的には毎日30分、多くても1時間以内、難しいときは15分でも机に座って参考書や病棟の資料を開いてみてください
まとめ
糖尿病看護の知識は看護師として必須です
糖尿病に強いと、どの科に行っても本当に強みになります
毎日少しずつコツコツと継続していきましょう
努力は必ず成長につながります
最後まで読んで頂きありがとうございました
おとうさんナース
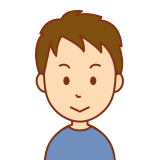
不明な点や質問がありましたらお気軽にお問い合わせください
看護師の方に向けて誠意を持って書いていますが、個人的な体験と意見が含まれていることをご承知ください









コメント